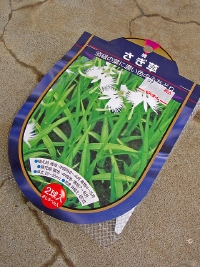2009年06月28日 コーヒーの花
いつもコーヒーの豆を買いに行く近所のお店で、コーヒーの種をもらって植えております。それは3年前のことで、ちゃんと芽が出て今は30センチくらいの木になりました。5本育っていましたけれど、そのうちの1本は枯れてしまい現在4本です。
先日・・・そのコーヒーの木に花が咲きました!
真っ白い可憐な花です。大きさは小さく、桜の花一つ分程度でしょうか。
花は3日ほどでしぼみました。育てている植物に花が咲くのはひとつの節目であります。無事に育っているものとしてうれしく思います・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2009年09月07日 今秋の収穫 <零余子>
自然薯(じねんじょ:山芋の一種)をアパートの庭に植えて二年目。
今年もつるには零余子(むかご)が出来はじめました。これは地上の茎に出来る小さな種芋なのです。山芋類の植物は地面の下と上とに両方繁殖できるすべを持っているという訳。育てていて途中でそれが分かったので、今年は零余子を植えて山芋の増産計画を立てました。
しかしながら、夏の日照量が少なかったので生育は今ひとつよろしくないのです。葉は昨年に比べてひょろひょろで勢いが足りないと思われる。これでは地下の親芋を掘り起こすのも期待できません。いっそのことそのままにして、来年の種芋に回した方が良さそうです。
・・・なので、今年も零余子だけを収穫して炊き込みご飯に混ぜて頂くことにします。零余子は9月中に何度か採れることでしょう・・・
写真上は壁際に植えた自然薯の隊列
半分くらいは芋虫などにやられてしまいました(汗)それにしても・・・自然薯は未だに花が咲いた所を見た事がありませんし、蛾はどうやってこれが山芋の葉だと判別して卵を産むんでしょうか?同じツタ系植物でも朝顔の葉に間違えて虫が付くことはありませんね?謎ですね・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2009年09月23日 彼岸花
今日は秋分の日であり、お彼岸ですね・・・
お彼岸は・・・
本来 極楽浄土に想いをはせる日で、浄土思想からの仏事だそうです。
それと同時にこの時期に咲く花があります。
それが「彼岸花」
地面から一本の茎が伸びてその先にもじゃもじゃした赤い花が咲きます。
一見異様な雰囲気すら感じる存在。
最近では園芸種と思われる白いタイプも見かけるようになりました。
その花言葉は「悲しい思い出」「再会」「情熱」「独立」「あきらめ」・・・
何だかもの悲しいイメージが含まれておりますね・・・
更にこの花の異名(地方によっての俗称)が凄いです。
「死人花」「地獄花」「幽霊花」「剃刀花」「狐花」「捨子花」
縁起が悪く、不吉なイメージがついてまわるのは少々可愛そうです・・・
この花は群生するので、写真に撮ると花同士がくっついて見え、
赤い塊になって写ってしまいます。
色飽和もしやすくべったりと締まりがありません。
なかなか手強い被写体です・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2009年09月27日 オナモミの実が採れそう・・・
今年の春に長津川緑地で拾ったオナモミの実(上)
いわゆる「ひっつき虫」です。
オナモミは、昔よりいつの間にか服に付いているものなので、どんな植物なのか?その正体は実際に確認した事がありません。ネットで調べてみればすぐに出て来ますが、実際に自分の目で見てみたい。知識だけのものと実体験のソレは 全くイコールのものでは無いので・・・
→NPO欄 2009.4/12 自然観察レポート5 <長津川緑地 2>
NPO欄のコメントへ飛ぶ
そのオナモミも、ご覧の様に立派に育ちました(中)
かなり水を必要とする草みたいで、すぐに土が乾きます。元々湿原に近いところで実を拾ったので、なんか納得するものがありました。
そして・・・ここ一週間ほどのあいだに、茎と葉の付け根からつぼみ?かと思えるものがふくらみ始めたあ(下)花が咲くのかな?それからここに実がなるんでしょうか?何だかすでにオナモミっぽい雰囲気がありますが、花が咲く前に実がなることはあり得るのか・・・
綺麗な実がたくさん出来たら面白いので、隣の空き地に撒いて増やしてやろうかなと目論んでいます(笑)
2009年09月30日 実の成り方が判明・・・
3日前の27日に、春先に拾ってきて鉢植えにしたオナモミの実がなりそうだとコメントしました。今日見てみると、もうその兆候が見え始めました。
花が咲くのか?と思っていたら、この松ぼっくりみたいなのがもう花のつぼみなのですね!?気がつきませんでしたけれど、その表面をアップでみると珊瑚の触手のような小さな雄しべみたいなのが所々に出ていました。そして、一部の塊はトゲトゲが伸びて「ひっつき虫」の方にに成ろうとしています。
野原の中で、オナモミはこんな形で自生しているのですね・・・
小学生の時にズボンに付けてきて その存在に気がついて以来、かなりの時間がたちましたが、今やっとその正体が分かりました!実が完全体になった所で、ばっちり記念写真を撮りたいと思います。ネット上の植物図鑑で探してもあんまり良い写真が無いので・・・
左の写真、左端の方にハナグモの一種がいます。花に近寄ってきた小さな虫を狙っているのでしょう・・・
Nikon D40 ISO400 画質モード「鮮やかに」RAW
SIGMA 105Macro F2.8→6.3 1/10sec -0.7EV
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2009年10月09日 立派なオナモミの実がなりました・・・
ついに立派な実に成長しました。セーターなどに張り付くトゲトゲの突起もご覧の通りです。後でクローズアップした写真も撮ろうかと思います。
このトゲトゲがマジックテープのヒントになったのは有名な話です。末は アメリカNASAが開発した宇宙服にも採用されて、船内で体を固定したりするのにも使われる様になった・・・自然から学ぶインスピレーションは素晴らしいものがありますね。
拾って来た「たった1個の種」でずいぶん楽しむことが出来ました・・・
ちなみに私が拾ってきたこの種は、外来種である「オオオナモミ」であるようです。それ以前から日本に広く分布していた「オナモミ」はトゲトゲが少なく、見かける事もありません。すでに絶滅危惧種に近い存在みたいですね・・・
Nikon D700 ISO800〜1000 絞り優先モード JPEG
SIGMA 150mmMacro F2.8→F10
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2009年10月11日 オナモミの実のマクロ撮影
先日 予告した通り オナモミの実のクローズアップを狙ってみました。撮影は10円玉を画面いっぱいに写すことが出来るベローズを使用。久しぶりに使ってみましたが、今回はなかなか手強い被写体でした・・・
通常は卓上にて完全静止した物撮りばかり。それが今度は植物ですけれど、こいつは微風でも揺らぐほど不安定な被写体。ファインダーの中で、オナモミの実一つ分の幅で左右にゆらゆらと行ったり来たり。余程速いシャッタースピードで切らないと画面の中央に収まりません。でもシャッター速度を上げるとアイリスを開けなければならず、すると被写界深度が浅くなってとげとげにピントが合わない。っで、ISO感度を上げたくなりますが、使用したFUJIFILM S5Proはそれ程高感度が強いとは言えないのでISO800が上限ですね・・・
結局揺れているものを撮るのに、何十枚も撮ってその中から良い一枚をセレクト。ところが、画像処理している最中に気がつきました。実をひとつもいで、机の上に置いて撮ればいいんじゃん!わざわざ何を面倒臭いことをしているのでしょうかね(苦笑)
まぁ、卓上で撮れないケースの練習をしたと思えばいいのかな?と考えつつ、画像をアップします・・・
FUJIFILM Finepix S5Pro ISO800 1/160 ミラーアップ+セルフタイマー
Nikon Bellows PB-4 + SIGMA105mmMacro F2.8→16
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2009年10月29日 エンゼルトランペット
最近割と見かけるようになった大柄の花があります。枝に出来た大きながくから垂れ下がるようにラッパ型の花が咲いている。不自然なまでに大きな花ビラはもの凄く目立ちます。ピンクや黄色・白などのバリエーションがあってほんのり甘い香りもします。
エンゼルトランペット
茄子科の植物だそうですが、これは草では無くて木なのだとか。別名「木立朝鮮朝顔」とも言うのでそちらの国の花かと思ったら、インドや中南米産が多いとのこと。素性がよくわからない存在です。
驚くのは、その花が咲いている期間がとても長いのです。うちの近所に咲いているやつも最初に見かけたのは8月末だったと記憶している・・・一つが枯れても次から次へとつぼみが出来て連続開花。結局二ヶ月間もの間、ずっと目にしておりますね。生命力がもの凄く強そうでちょっと可憐さには欠けます。
「夏のひまわり、秋のエンゼルトランペット」という感じで、私の季節のイメージの中に定着しつつある花であります・・・
FUJIFILM Finepix F31fd 接写 クロームカラーモード
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年02月08日 すずらんの鉢
ホームセンターに立ち寄った時に、園芸コーナーにてすずらんの鉢を見かけました。もうつぼみが付いています。毎年近所で咲いているところを見ていますが それは桜の後のはずでは?つぼみのままあと二ヶ月近く変化しないとは思えないのですけど・・・
興味が出たので買ってきました。
やはりつぼみがついていると言うことは温室育ちの個体なのか?そのまま庭に植えたら恐らく枯れてしまうのではないか?そんな心配があって今のところ部屋の中。買うときに店員さんにちょっと聞けば良かったなー。
これはエビネと一緒で、条件が良ければどんどん増えます。暖かくなってきたら庭のどの辺りで増やそうかと思案中です・・・
追 記
ちょっと調べてみましたら、3月から4月いっぱいにかけてが開花時期みたい。意外と寒い時期に咲く花でした。それでもこの個体は生育がやや早めなのではないでしょうか。庭への植え替えについては更に思案中・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年02月14日 すずらんの開花
先週の8日にホームセンターで買ってきたすずらんのつぼみが開きました。これはグッドタイミング!ちょうどレタリング(文字)の周りに蔦(ツタ)を絡ませるデザインをやっている所だったので、これを参考にすることにしました。
こういうのは壁紙などのパターンを作るときによくやる手。既製品では、イギリスのウィリアム・モリス氏の図案が有名(過去にも一度コメントしました)同様のものが浴室や洗面所の壁紙に多く その名を知らなくても、誰しも見たことがあるはずでしょう。半日ほど作業して蔦のデザインと文字を組み合わせたレイアウトが出来ました。こういう利用価値があるので「植物の写真」は日ごろもっとたくさん撮っておいた方がよさそうです。なにしろオリジナルのものを作らなければならないので…
そういえば、3月になってから咲くと思われていたすずらんですけれど、2月中旬でもう咲いてしまった。部屋の中に入れたままだったからですね。これも怪我の功名という奴かな…
2月18日 追記
小さな可憐な白い花が鈴なりに。現在最大限に花びらが広がっています。
普段見えない角度から撮ってみました。
そして…ラン科の花だけあって、部屋の中はその香りでいっぱい。昔 小学館の小学二年生あたりの付録で、こすると鈴蘭の香りがするカードがついていましたっけ。香りから思い出す記憶もありますね…
Nikon D700 SIGMA105mmMacro F2.8→6.3 1/250 ISO1600
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年04月02日 ウラシマソウの復活
昨年のこと、近所の谷津田の斜面で雑木林の伐採がありました。多くの植物が切られてしまいましたが、そこに植わっていた「ウラシマ草」を数株持って帰りました・・・
ウラシマ草は、花弁が食虫植物のうつぼかづらの様な形をして少し気味が悪い感じ。茎の模様が蛇の模様に似ていることから「まむし草」とも呼ばれます。実際には多くの亜種があってそれぞれ特徴が違うのですが、見た印象が似ています。
ウラシマ草はサトイモ科テンナンショウ属の植物。毒があるが根の一部は漢方薬の材料にもなるそう。花弁の様に見える部分は「仏炎苞」と呼ばれるもので、有名なミズバショウの花と同じようなもんでしょう。観賞用に園芸ショップで売られているもので「雪餅草」というのがありますが、5年くらい前に買ってきて一度庭に植えたことがあります。土が合わず?たったの一週間で枯れて消えてしまいました(写真 上)
っで・・・昨年 持って帰ったウラシマ草ですけれど、アパートの庭に植えたところ、やはり一週間で枯れてしまいまいた。直射日光が長時間当たらない日陰よりの場所をちゃんと選んだのに何故駄目だったのか?やはり土が合わなかったのかな。失敗は繰り返された・・・それが、昨日庭を見たときに・・・何と昨年植えた場所に新しい葉が出ているではありませんか!(写真 下)しっかり根付いて復活成長しておりました。もともとサトイモ科の多年草なので、根が生きていればそこから芽が出るわけです。なんかうれしい。
新しい場所の環境に順応してしっかり育てば、夏頃にはあの毒々しい花が見られると思います。とても楽しみです。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年04月12日 コケの管理の難しさ
久しぶりにコケの話を・・・
もう10年以上管理維持しているコケ玉があります。私がコケの栽培に強い関心を持ちはじめたのは、オオクワガタの繁殖を始めた時期よりずっと昔です。理由は自分でもよく分かりませんがとても魅力を感じます。特に観察対象にしているのは、コウヤノマンネンゴケの類。そのコケの管理はとても難しく、一般の観葉植物の知識はほとんど役にたちません。
それでも今までそこそこうまく維持できていたのですが・・・この1年ほどの間に、その大事なコケ玉のいくつかがすっかり衰えてしまいました。特に岩に活着させた大玉が瀕死の状態に・・・何故だかは理由がさっぱり分からない・・・
ところが、今日思い切って枯れた部分をトリミングする作業をしていた時に、原因?が判明しました。コケ玉を入れていた水槽内にワラジムシが何匹もいるのを発見!ワラジムシはダンゴムシの近似種で丸まらない奴ですね。虫好きの私でも、あまり気持ちの良い存在に感じません。そしてそいつらは、出たばかりのコケの柔らかい芽の部分をかじり取ってしまう可能性が高いと思われる。まったくいつの間に進入したのでしょう。以前、陽に当てるために表に出していた時に入ったのかな・・・
本来なら今頃は、綺麗で若々しい緑色に覆われているはずの岩が、これだけ貧相な状態になるまで気がつかなかった。全く油断してました。「風の谷のナウシカ」ではオームが森を守っている設定でしたが、そのモデルのはずのダンゴムシやワラジムシは、自分たちの住み家を荒らしてしまうのか!?現実はシビアでありますね・・・
写真 上は3年前の状態 下は今日撮った とほほな状態の一つ
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年04月19日 極彩色の花桃
桃の花はひな祭りの頃に咲くものが一般的ですが、花を観賞するために品種改良された園芸種に「花桃」という木があります。桜より遅い開花です。ピンク色の濃さが尋常でなく、まるで造ったようなわざとらしい極彩色ですね。私は最初造花かと感じました。
花を近くで見ると、普通の桃の花と違って花びらは縮れて細長く八重咲きの花でした。印象としてはマンサクの雰囲気がします。
この花のことをネットで調べてみようとぐぐってみましたら、ごっつーエグい色味のピンク色がたくさん出て来ました。鮮やかすぎて私はあんまり好きではないなぁ・・・少し離れて眺めるのがよろしいかと思います。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年04月24日 コウヤノマンネンゴケ
この所細かいものをちょこちょこ買っていますが、通販も時折利用しています。しかも今までではあまり考えられなかったものが購入対象になってきました。それは「植物」・・・
先週、長年維持管理しているコケ玉が虫にやられて半枯れ状態になってしまった事を書きましたが、ネットで調べてみた所、コウヤノマンネンゴケの入荷をしている花屋さんを見つけました。ほんの5年位前では 通販で扱っていなかったと思いますので少し驚き・・・でもこういうレアなものまで手に入る時代になったのですね。
コウヤノマンネンゴケは、針葉樹林の落ち葉が堆積した腐葉土の上に生えるコケです。かなりサイズが大きくなります。コケというより小さな杉の芽のようなイメージがありますね。基本的に日陰の植物なのですけれど、若干薄日が射す程度の明るさは必要。そして、少し湿度があってそよ風がある程度の環境が望ましい。このコケは地下茎を伸ばして四方八方に増えて行きます。特徴敵なのはその地下茎が完全に土の中にあるよりは、落ち葉の層の上の方に根ざしている方が好ましい。つまり根にも空気若干が触れている状態が良いと思われます。以前、山を歩いた時に生えている環境調査をしっかりして来ました。その上でそういう環境を人工的に造ってやるのは簡単ではありません。そこに固有のコケを管理維持する苦労があります。定期的に霧吹きで湿度を保ってやることが肝要ですね・・・
コケの魅力は、小さな限られた空間の命を一生懸命守ってやることです。それを「何故?」と問われると簡単には返答できませんが・・・例えるならば、サン=テグジュベリ氏の「小さな星の王子さま」の世界でありましょうや。1本の草に一生懸命水をやって愛でる行為には何かあるのでは無いかと自問自答しています。
この小さな世界は、私が感心を失ってしまえば やがて死で覆われることでしょう。綺麗で健康的な緑を見たいと私が想い続けるならば、それはそこに在り続けるかと思います・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年04月25日 オダマキの花
アパートの駐車場の脇に、毎年生える雑草があります。同じ所から生える所を見ると、多年草かと思われる。ちょうど今の時期に花が咲きますので、引っこ抜かずに毎年見ています。生えて居るところがコンクリートの隙間からなので「根性大根」に匹敵する存在。今日は日差しがあって特に花が映えました。良い感じです
一見したところ、フクシアという洋花にちょっと似ていますね。花の付き方が特に。でも、この花は身近の空き地などでも見かけますから 恐らく国内種?それとも種が拡散した何らかの園芸種?一体何の花なのでしょう?
そうこうしているうちに、mixiのブログでこの花の情報を頂きました。それによると、どうやらオダマキの一種らしい。高山地帯に生息している野生種と、品種改良した園芸種に分かれて様々な種類があるようです。ネット上で調べたところ、この駐車場に生えたものは園芸種みたいだと分かりました・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年04月27日 サンシャイン牧場よりリアルな種を・・・
mixiというSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)には、最近 簡単に遊ぶことの出来るゲームのアプリが増えてきました。ブログの合間にちょこっと時間つぶしをする程度の簡単な遊びです。その中に「サンシャイン牧場」という育成シミュレーションゲームがあります。種を植えて育ってきた所で収穫するとポイントが上がります。最初の頃は一生懸命水をやって世話をしていました・・・が、実は最近あまり積極的にやっていません。なんかもう飽きてきた・・・作り手の思惑が見えてしまって面白さがかなり減退してしまいました。バーチャルな植物の種は植えれば必ず生えてクローンが増えます。当たり前過ぎて予想外のアクシデントは皆無ですね。当然の結果しか無い・・・
私としてはやはりリアルなプランツ栽培の方が刺激があって楽しいです。昨年秋に庭で収穫したいろいろな種がそろそろ植えても良い時期に。手始めにホトトギスの種を庭の一角に蒔きました。うっかりしていたのは、稲は泥に蒔いておかなければならなかったのを怠って時期が過ぎてしまいましたね・・・
写真に写っているのは「じゅず」「ススキ」「ホトトギス」「稲」「正体不明の種」・・・それ以外にも、ムカゴやオナモミ、ザクロなどがあります。それらは今、庭に適当に植えると、地虫にやられてしまう可能性も高いので、一旦プランターに蒔いて、芽がちゃんと出てから移植した方がいいかも知れません。
連休中にやろうと思います・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年05月02日 ホオズキは地下茎で増える
昨日は、この春先放置していたせいで草ボウボウになった花壇の草刈りを少々。ほんの2~3週間ほどで雑草がこんなに生えるとは!天候があまり良くなかったのですが、それでも一旦生えると伸びるのは速い。油断しているとあっという間に混沌とした状態になってしまいます(汗)雑草を排除すると、そこには過去に意図して植えた園芸植物の芽などが出て来ています。ちょうど良いタイミング・・・
庭には、毎年 綺麗なホオズキの実がたくさん成ります。元々それは、縁日で買ってきた一鉢から分かれて増えたもの。最初は植えた場所 半径50センチほどの範囲で見られていたので、落ちた実から芽が出たのだろうと思っていました。ところがこの二年ほどの間に距離が伸びて3m位先にぽつぽつ生え始めた。
恐らく、鳥がほおずきをつついて、その種が落ちたからだろうと思っていました。でも、昨日一部の芽を掘り起こしてみたところ、こんなに長~い地下茎でつながっていました(写真 中)なるほど、こういう植物だったのか!すると、目の前にたくさんはえている株は、全部繋がっている可能性もあるわけだ。
あまり範囲が広がりすぎるとちょっと邪魔になるので、この夏はホオズキエリアを限定して管理したいと思います。この若葉には特定種のカメムシがたくさん付きます。ちゃんと世話しないと、葉が穴だらけになって見苦しくなってしまうし気持ち悪い。秋口に綺麗なホオズキの実を拝みたいですね・・・
写真 上は夏頃の様子、下は晩秋に地面に落ちた実
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年05月22日 実家の畑で農作業
嫁さんの実家には畑がありまして、毎年そこで採れた野菜をお裾分けしてもらっています。その有り難さは小さなものではありません。嫁さんから聞くところによれば、畑は嫁さんのお母さんが独りで世話しているとのこと。うちでは何時もその成果を貰ってばかりなので恐縮でありました。それが理由の全てではありませんが、私はNPO活動で農業に関心が高まったこともあり、まずはお手伝いからやってみたくなりました。日頃の忙しさの中で、どのくらい出来るのかはやってみなければ分からない。でも、とにかく始めないと何も変わらないので、今日から始めました。
本日は、落花生(ピーナッツ)の種を植えました
1.まず 苗床を作る為に、鍬で畑に溝を掘ります。
2.溝に肥料を蒔きます。
3.落花生は土中に豆が出来ますが、それを喰う地虫を遠ざけるために
オルトラン(殺虫剤)を追加散布します。
4.落花生の種を二粒ずつ、数十センチ感覚で蒔きます。
5.軽く土を被せる。
6.ネットを被せます。
私は落花生が地上の茎の何処かに成るものと勘違いしていました(苦笑)実際は土中に出来るとのことで、地虫対策は必須のようです。オルトラン(殺虫剤)を使用しないと虫だらけになるとのこと。土中だと虫が湧いても気がつかないでしょうね。そして、大事なのが、落花生の芽が出たころには、カラスや鳩などが若芽をついばんでしまうので、それを防ぐためのネットが必要なのですね。そういうことは、やはり経験が無いと分からないことです。今日は色々農業のコツを勉強させてもらいました。いずれはもっと積極的に畑作業をやれれば言うことありません。
落花生は約10日ほどで芽が出るそうです。その頃にまた畑を訪れて発芽の様子を観察したいと思います。これから雑草もたくさん生えてくるのでその対処をしないといけません。写真の猫は実家の飼い猫のジョン。下の写真は落花生の発芽の様子(以前撮ったもの)
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年06月07日 落花生の芽
5月22日に、嫁さんの実家(農家では無いが畑がある)にて、落花生の種を植えるのを手伝った件。
約10日ほどで芽が出たそうです。ちょうど二週間ほどしたところで一度様子を見に行くつもりだったので、行って来ました。もうだいぶ苗が伸びていて、カラス避けのシートはとっくに取り払われていました。これからは定期的に様子を見に行って、雑草取りなどをやろうと思います。
ちょうど見に行った時刻は夕方前とはいえ、まだ日差しが強い時間。ここしばらくお湿りが無かったので、土はカラカラに乾いていた。嫁さんのお母さんに「水撒きをした方が良いのですか?」と尋ねると、「やるならば朝か夕方のどちらかに・・・」という答えでした。熱い日照りの最中に水をあげても直ぐに蒸発してしまうし、かえって植物にとってよろしくないらしい・・・昼に水をまかない方が良いというのは、近所の園芸好きなおじさんからも聞いた覚えがある。そういうのは、長年の体験から来るうんちくですよね。理論よりも大事だったりしますので、貴重なアドバイスです。私は鉢植えの植物などには、自分の時間の都合で水をやっているので、けっこういい加減にやってますね(汗)
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年06月25日 白いネジバナ
ネジバナはちょうど今の時期、梅雨の最中に花を咲かせる野草です。モジズリ・小町欄とも言う。私もブログを始めてから毎年観察しています。この植物の葉っぱは、普段こじんまりと生えていて、そこいらの雑草と区別がつかないでしょう。それが梅雨に入ると、一本の茎が凄い速さでひょろひょろと伸びてきて、そこに小さなつぼみを付けます。そして花が咲き始めるとあら不思議!どんどんねじれて螺旋状の面白い花になります。
特別な花ではないので、家の身近で探しても所々で見かけます。ただ、咲いている期間が限定的なので気がつかない人も多いかも知れません。
4年前に近所で「白いネジバナ」を見かけた事があります。それは野生種では見かけないので、人が作り出した園芸種なのかと思います。その後、園芸ショップで探した所、やっと昨年一株だけ売っているのを見つけました。鉢に植えて約1年間世話をしていたのですが、ずっと雑草を育てていた様な気分でした。成長がやや悪く少しひょろひょろしています。
現在 茎が伸びて約一週間たち、やっと花が咲き始めた。この花は、短い時間一生懸命咲いて、種を作るとあっという間に萎れてしまう。そしてまた雑草に紛れて1年を過ごす多年草。他者におのれの存在を示すのはほんのわずかなひとときなのですね・・・そういう可憐さがとても気になります・・・
白いネジバナを植えた鉢には、近所で取ってきた野生種のピンク色の株も植えてあります。紅白のネジバナの競演が見物です。写真3枚目は最近野外で見かけた野生種(コンデジにて撮影)
FUJIFILM S5Pro ISO320 絞り優先モード
SIGMA 150mmMacro F2.8→9 三脚使用
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年07月12日 擬宝珠 <ギボウシ>
写真(1〜2番目)は ブログを始めたばかりの2006年5月頃。仙台にある山寺の立石寺境内。そこで所々に直径が50センチを超える見事な放射状の葉っぱを見かけました。ずっと気になっていたのですがその正体が分からずじまい。それが最近近所の至る所で見かける様になってきたし、園芸ショップにも出回っているので驚きました。一株買って来ました(写真 3番目)
植物の正体は擬宝珠(ギボウシ)
橋の欄干にある「タマネギの様な形をした装飾物」が擬宝珠。この植物の花のつぼみが同じ様な形をしているので、そこから名をもらったそう。紫色の綺麗な花が咲くそうです。短くギボシとも言うらしい。日本に元からあった植物だそうですが、ガーデニングが盛んなイギリスに渡り品種改良された園芸種(ホスタ)が最近逆輸入されているとか。さすれば、買って来たのも園芸種なのか?店員さんの話によると、あんまり大きなサイズには達しない品種なのだそうです。
しばらくは鉢植えのまま育てて、多少大きくなったら庭の何処かに移そうと思います。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年07月29日 烏柄杓 <カラスビシャク>
家から鉄道の駅に向かう途中、線路際の土手に珍しい植物を見つけました。
それはもう半月ほど前のことです(写真 上)これは、私が以前より栽培にチャレンジしたことのあるウラシマソウ(サトイモ科テンナンショウ属)の近似種に間違いない?葉っぱの形や鎌首をもたげた形の穂は特徴が一致します。この草はかなり昔に、山野草の草盆栽に生えていたのを見た記憶もある。確定ではありませんが、これはサトイモ科ハンゲ属の烏柄杓(カラスビシャク)ではないだろうか。何でこんな所に生えているのか?と言うと・・・恐らく鳥の糞に種が紛れていてここで芽を出したのでしょう。関心がありましたが、そこは柵の向こうの線路際で入れない(汗)
ところが、今日外出した際に、線路際の雑草を定期的に伐採する作業員が来ていました。土手の草はすでに最盛期を過ぎて枯れかけている。でもこれはチャンスと思い「作業大変ですね」と声をかけました。「ちょっとそこにある草が欲しいのですけど・・・」と相談すると、快く採らせてくれました。土手は比較的柔らかい土で、ちょっと掘り起こすと 根っことその先に小さな球根があった。やった!これさえ手に入れば・・・さっそくアパートの庭の日当たり環境の近い場所に植えました。
上手く芽が出て復活するとうれしいのですが、それは来年の事でしょう・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年08月02日 烏柄杓の仏炎苞
数日前に近所で採取してきた烏柄杓(カラスビシャク)
・・・花にあたる部分を仏炎苞(ぶつえんほう)と言います。
それは、世間で有名なミズバショウやザゼンソウの穂と同じもの。
その中に種にあたる実ができます。肉穂花序と言うらしい。
採取してきた茎に元気を取り戻した個体がありました。
丸く被さった葉が少し開いて肉穂花序が顔を出しました。
これも植えるとしっかり芽が出るのか確認したいですね・・・
烏柄杓の球根は漢方薬の半夏(はんげ)というものらしい。
それも今回調べてみて分かった事でした。
珍しい植物だと書きましたが、けっこう認知度の高い薬草だったのですね・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年08月21日 こぶしの実
これは何か?と言いますと、辛夷(こぶし)の木の実です。
辛夷はモクレン科の木なので、大木になってもその幹に似つかわしくない大きな花が咲く。そこまでは知っていましたが、その実はとても不思議な形でした。モコモコした繭が繋がったような奇妙なかたち。一房取ってきていたのは最初緑色だった。それが見る間に茶色に変色して、亀裂が入ると中から種が出て来ました。まるでビスタチオの様な感じ。でもちょっとグロテスクでもあるかな?
これ・・・植えたら芽が出るかしらん?
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年10月01日 彼岸花
もう10月になりました。 今満開の花があります。
彼岸花
先週 近くの谷津田に行った時に撮ったもの。
ビデオ撮影が主だったので、コンデジでおさえた程度のものですが。
ピントも満足に合ってなかったりしますけれど(汗)
この被写体はとても個性が強くて、フレームに収めるのが難しい。
本来ならちゃんと一眼レフで時間をかけて撮りたいものです。
今年は酷暑の影響があって、彼岸花は開花時期が一週間遅れました。
そしてまた、若干力強さが弱く、全体的に貧相な印象すらあります。
来年また同じ場所で 赤い絨毯に期待したいと思いました・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年12月18日 厄除けと根性
師走の慌ただしい頃合いですが、クリスマス・年越し前の縁起を担ぐ意味も兼ねて、身近のスナップを二枚。
左は正月の飾りにも使われる南天。千両や万両と同じような真っ赤な実を付けた目立つ植物です。実家の茶庭に植えてあるもの。右はカタバミの三つ葉なのですが、生えている所が普通でない。コンクリートからダイレクトに育っている。ひび割れた隙間などからはよく見かける事がありますが、こいつはその上を行っていますね。
南天は「難転」と読んで「難を転じる」という古来よりの厄除けの語呂合わせ。
このカタバミは「根性」の一言が相応しい。
両方合わせて、元気の素になぞらえたいと思います・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2010年12月25日 畑の落花生は無事収穫されました
夏以降、子供の件でホントに慌ただしくしていましたので、色々なやりかけの事が中途半端になってしまいました。先日 嫁さんの実家から届いたもの。それは6月に、畑を耕して自分で苗を植えるところまでしていた落花生。その後の世話管理は?・・・
・・・結局 私は畑を放ったらかしにして、8月以降は水やりにも行っていなかったのでした。その後は嫁さんのお母さんが一人でせっせと世話をして、立派に育て上げ、秋以降にしっかり収穫作業まで行ったそうです。手伝うと口では言っておきながら、私はすっかり蚊帳の外に。豆がなっている頃には一度も畑に入っていませんね(大汗)
収穫された落花生は、その後乾燥させて火を通し、市販されているものと同じ様な姿となって、我が家にもお裾分けをして頂きました。ほんとに恐縮してしまうばかり・・・農業も、一日たりとも手が離せない「何かを育てる」事に変わりなく、生半可な関わり合いで投げ出していた私には何も言うことはありません・・・落花生、美味しく頂戴いたしました。
写真 上 生い茂った落花生の木(8月10日撮影)下 収穫の成果
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年02月16日 ヒラタケ
冬場になると、私も好きな昆虫の話題から自然と遠ざかります。実はその間にもオオクワガタの菌糸瓶などは最低限の維持管理作業があるのですが、地味なので触れることも無かった。
そういえば、菌糸瓶とは何か?・・・
この商品があるからこそ、一般のど素人でも、クワガタムシのブリーディングが出来るようになったのです。最初に商品化した人は偉大ですね。具体的に説明すると、クワガタムシの幼虫は、朽ち木の中でその腐朽した木材の繊維を食べて大きくなる。その生態を長年研究した人が、そこにきのこ菌が繁殖していることに気づいた。そこでオガクズにきのこの白色腐朽菌を接種して、人工的に白腐れ状態を作ったとのこと。それが菌糸瓶という商品。安く市場に出回る様になったのが、1999年頃のオオクワガタのブームからだと記憶しています。その頃は1本が数千円しました。その直後に外国産カブトムシ・クワガタムシの生体の輸入が解禁になり、菌糸瓶の価格もこなれてきて今や千円以下に・・・
この菌糸瓶のキノコ菌は「オオヒラタケ」「ヒラタケ」「カワラタケ」などの菌糸だと言われています。菌は生きているので、菌糸瓶の扱いは環境を選ぶ。流通量の多いヒラタケ系の場合は、室温19~25度くらいの室温で管理すべしと、クワガタ飼育の教本に書いてある。それ以上だと菌糸が劣化するし、以下だとキノコになってしまう!?
この2月は関東でも雪が降ったりして気温の低い日が多かった。うちでは菌糸瓶は事務所のある棚の中に並べて置いてあるのですが、この一週間ほどの間 ちょっと目を離していたら凄い事になっていました。ご覧のように、立派なキノコが生えていた!こりゃやばいな。キノコになってしまうと、菌糸瓶の中の栄養分が使われて劣化してしまう。オオクワガタの幼虫の成長に影響が出ます。近日中に全取っ替えだ。
せっかく生えたヒラタケのキノコ。美味しそう?ですが、これは食べられる種類のはずです。でも、下の瓶で幼虫が舐めていたものなので何か嫌だ。今までも一度も菌糸瓶からのキノコは食べたことがありません。大きな天変地異でもあれば非常食になるのかも知れませんが(苦笑)
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年03月28日 シキミの花
アパートの庭に植わっている八角に花が咲きました。
この植物の花は私は見るのは初めて。別名 トウシキミ。
八角は・・・その実を乾燥させたものが中華料理の材料として
店頭で売っています。スターアニスという奴がそう。
これからどんな実が出来るのかちょっと注目したいですね・・・
29日15:30 追記
知り合いの方からご指摘を頂戴しましたので、
この植物について調べ直してみました。するとどうやら八角
(トウシキミ)では無くシキミである可能性が濃厚であります。
シキミは毒性が強い植物なので、庭に猫の小太郎が出た時にかじったら大変!
さっそく根っこごと抜いて処分しました。
ブログに情報を上げたことで詳細が判明して良かったと思います・・・
やれやれ・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年04月3日 白いモクレン
今年は桜よりも前にモクレンの花が栄えました。
特に晴天の青空をバックにした白いモクレンは最高!
これ以上になく明るく輝いて見えます。
iPhoneで撮ってもなかなかのコントラスト。
とても気持ちが良いです・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年04月5日 今年もウラシマソウが生えました
春先に私が楽しみにしているのは、庭に植えてある多年草の植物が芽吹くこと。中でもいくつかの山野草の類は、平地に根付くかどうか難しい一面もあるので、毎年注目しています。
ウラシマソウもそのうちの一つ。重要な日当たりの具合は場所を選んで植えました。でも、土の成分や湿度などは問題で、なかなか難しい移植条件となっています。それでも二年続けてしっかり芽が出ました。これには感動を覚えます。
もっともこの後が問題で・・・アパートの坪庭には、異常なほどダンゴムシ・ワラジムシが多く湧くのだ。それが柔らかい若芽を穴だらけにしてしまう!?それで、昨年もせっかく生えたウラシマソウが初夏まで持たなかったのです。今年はその辺りの対策をしようと思うところ・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年04月7日 近所のさくら
東京ではもう桜が満開なのですね。
気がついたらすでに4月も七日目になっています。
例年でしたら私も桜を見に出かけている所ですが
今年は今の所その予定を立てていません。
家の近所の公園の桜も見頃になっておりました。
せっかくなのでレンズを向けてスナップを・・・
夕刻の逆光気味の桜は、いつもと少し違った表情でした・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年04月7日 桜桃(ゆすらうめ)
一昨年に実家から一本の小さな苗木をもらい、庭に植えていました。
名は桜桃・・・そのまま読めば「おうとう」ですが、「ゆすらうめ」と
一般には呼ばれているらしい。
桜梅という当て字もあるみたいで紛らわしいネーミングです。
元々が中国原産で、江戸時代より日本に根付いた小型の落葉低木。
6月頃に小さくて真っ赤なサクランボが成ります。
そのゆすらうめが桜の時期に合わせて満開となりました。
やや線の細い可憐な花びらに春の柔らかさを感じます。
私は、花に関してはこのぐらいのお淑やかな感じが好きです(笑)
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年04月15日 黄花モクレン
黄色いモクレンがあります。
園芸種でエリザベスと言われる品種。
アパートの庭に植わっている奴が先日咲きました。
白や紫の品種と少々印象が違いますね。
綺麗に咲いている期間は短いので近くで咲いていたらお見逃し無く・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年05月4日 公園の花たち
連休中の家族サービスということで、今日は船橋アンデルセン公園に出没。
娘のことちゃんはまだ小さい・・・ストレスを与える様な遠出はできませんので。
本日の空模様はやや霞んでどんよりしていましたが、紫外線は強く
時折初夏の日差しにもなりました。アンデルセン公園は、八重桜も終わりに
かかり、今は藤とポピー、それにパンジーなどが満開です。
そしてミツバチがたくさん飛び回って一生懸命働いていました。
今日は一眼レフデジカメに35mm単焦点レンズを一本つけて行きましたので
これでも目一杯花に寄って撮っています。蜂をアップで撮るには
やはりクローズアップレンズが必要ですね・・・ 
FUJIFILM FinePix S5Pro Nikkor 35mmF2 プログラムオート
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年05月18日 オナモミの実を植える
今年の春は震災の影響があって、色々なことをおざなりにしてしまいました。
本来なら4月頃になると、庭には多くの植物の種などを植えて、
夏から秋にかけての植物の生育を観察するのが習慣になっています。
その種子は、前年の秋に収穫したもの。
「稲」「自然薯の零余子」や「数珠の実」、それに「オナモミの実」も、
年々採れる量が増えて来ました。少々タイミングが遅くなってしまいましたが、
オナモミの実を庭の数カ所に植えました。この植物は雑草であり、
綺麗な花が咲くわけではありません。
でも愛着を感じる植物なので、毎年その実を拝みたいと思っています。
オナモミの実のとげは、服にくっつきやすいので「引っ付き虫」なんて
言われ方もしています。
マジックテープ開発のヒントになった存在であります。
多年草であるホトトギス(2枚目)やほおずき(3枚目)は、
同じ場所で再生して、その葉がどんどん伸びてきました。こちらは順調な様です。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年05月22日 ヒルザキツキミソウ
本来の月見草は、日暮れ頃 花弁が開いて翌朝には萎んでしまうという、夜間に咲く花だという。それはなかなかお目にかかれない可憐な存在です。
一方で、昼間見られる俗に月見草と呼ばれるものは、ヒルザキツキミソウです。こちらは、今の時期に私の身近でもかなりよく目にする事ができます。ピンク色の鮮やかな花が群生している風景は、なかなか風情があって良いです。
その細い線の印象とは裏腹に、とても生命力が強くてどんどん増える。近所の線路際の土手なども、いつの間にかヒルザキツキミソウに占拠されて、綺麗な色彩に埋め尽くされております。意外と葉っぱが目立たないので、その花びらだけが印象に残る。目立ちたがり屋な奴らだなと感じてしまいますね・・・
写真を撮ったこの場所では、そろそろ開花の時期が終わろうとしていました。写真としては今一つな写りです・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年6月9日 名を知らない赤い花
最近は身近の灌木に、外来産の見知らぬ植物が増殖中です。
ごらんのこの赤い花が咲いている木もその一つ。
恐らく日本のものでは無いと思うのですが・・・
とても目立つ花なので、その正体が知りたいです。
いったい何という花なのでしょう?
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年6月10日 ザクロの花
庭のザクロの木に花が咲きました。
このザクロは、私が小学生の時に住んでた世田谷区のマンションの敷地内にあった木から、種を取ってきて育てている個体です。その後、そのマンションは取り壊されてしまい、そのザクロの木も無くなってしまいました(取り壊されるのを知って種を取りに行ったのが正しい順番)だから、私が採って来た種から生えたこのザクロは、親の木の忘れ形見的な存在です。
私は木にも愛情と愛着をしっかり感じて接しております。だから、私の幼少時代を知っているザクロの木の子孫は、私が守っていくべき存在だと認識しています。それは私の死生観から来るものでもあります。大事にしたいという自然な気持ち・・・
そのザクロの木に花が咲き、やがて実をつける風景は、私が小学生の時に毎年見ていた日常でした。私にとってそれは意味の深いことでもあります。
二枚目の写真は、昨年 この木になったザクロの実から採った種
そこから芽が出た1年目の苗木です。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年6月23日 今年のネジバナ
毎年今の時期にはネジバナ(小町欄)についてコメントしています。
梅雨の時期に咲く細長くてひょろひょろした一風変わった可憐な花。
今年も鉢植えにしてある株から花が咲き始めました。
ピンク色の野生種と白い色の園芸種を寄せ植えにしています。
紅白の競演が見られるので今年も楽しみに待っておりました。
数日前より花が咲き始め、それにしたがって蕾の並ぶ茎が
次第にネジレ始めました。ほんとに面白い花です。
これから一週間くらいの間 うちのネジバナは静かに開いて
小さな花見をさせてくれそうです・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年7月1日 ギボウシの花
一年前に鉢植えで買ってきた擬宝珠(ギボウシ)に花が咲きました。
葉っぱだけで一見地味な存在かと思っていましたが、こういう植物だったとは。
花の部分だけみればサフランの様です。
花が咲いたと言う事は実の様なものも成るのかな?
しばらく様子を観察してみましょう・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年7月14日 涼を呼ぶ 吊りしのぶ
梅雨明けと同時に予想を越えた酷暑になりました・・・
節電にも心掛けての毎日の暮らしはやはり楽とは言えない感じ。今年の夏場のエアコン温度は最初30度を予定していましたが、実際には28度まで下げないと自分もPCも熱でやられそうなのが分かりました。無理に我慢してトラブるのは馬鹿馬鹿しいので、やや省エネモードで頑張れば良いかなと考え直し・・・
さて、気分というのも大事で、見て涼しくなるものは効果があります。ホームセンターの園芸コーナーで、懐かしいものを見つけて来ました。
吊りしのぶ
シダの一種を 細木を組んだ苔台に植えて吊れる様にしたものが昔からあります。浅草のホオズキ市などでも見かけられると思います。私も5年位前に、一度買ってきてベランダに吊していた記憶があります。これがあるだけで、何か涼しい雰囲気が楽しめて良いのですよ。今回見つけたのは、完全な球形に編み込んだタイプで、下に風鈴が付いていました。風鈴は一つ一つに個性があるので、気に入った音のを選んで来ました。
「しのぶ」という名は色々な意味が込められているらしい。いわゆる「忍ぶ」であったり、「偲ぶ」であったり・・・涼につながる忍ぶという捉え方であれば、今年の省エネのスローガンにハマりますし。
しのぶは毎日しっかり水をやらないと直ぐに葉が萎れてしまいます。朝方バケツにはった水にぶくぶくと沈めてしっかり給水します。軽く水をかけただけでは直ぐに乾いてしまうのですね。涼感が続くようにしっかり水やりをしてあげたいと思います。そうそう、風鈴部分は鉄なので、直ぐに拭いて乾かさないと錆びてしまう。一シーズンで音が変わってしまいますので注意が必要かも・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年7月20日 ホテイアオイの花
ギンヤンマのヤゴを飼育している水槽(Insects蘭で紹介)には、ホテイアオイ草が浮かべてあります。何故かと言うと、これは水質浄化の為なのです。ホテイアオイは、その根から有害物質を吸い上げ、その結果 水が濁りにくくする効果まであるほど。更に、水中の余分な栄養素(主に窒素分)をどんどん消費して、富栄養化を防いでくれるのは、よく知られた習性ですね。
そのホテイアオイに今朝花が咲きました。紫色の上品で面白い形をした花です。見るのは初めてではありませんが、久しぶりにその美しさに触れて、改めてこの浮き草の魅力に関心が高まりました。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年9月20日 ミズヒキのつぼみ
これから秋が深まるこの時期になると、ミズヒキに綺麗な赤いつぼみが成ります。
この小さな赤い一粒一粒には、これから花が開く何とも言えない期待感が漂って趣深いです。
茶花にもよく添えられる脇役の存在ながら、その奥ゆかしさはその場の雰囲気に調和と品性をも生み出しているかのよう。有ると頼りになりますね。
ミズヒキには金色のキンミズヒキもあります。以前実家の茶庭に植わっていたのですが、何時の間にか枯れて途絶えてしまいました。けっこう環境を選ぶ植物なのかも知れません。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年9月22日 数珠玉(ジュズダマ)
そう書くと、仏事で使う数珠を思い起こしそうですが、これは植物の数珠のこと。実際には子供用のお手玉に入れたり、装飾品に利用する事が多いらしい。本来は水田の畦(あぜ)なんかによく生えている野草です。
うちのアパートの庭には現在この数珠玉がたくさん生えている。元は数年前・・・NPO活動で参加した「市民の田んぼ」の脇に生えていた株より、採ってきた数粒から増えました。なかなか繁殖力の強い植物です。
数珠玉の花はちょっと変わっています。雄花と雌花が別々に咲いて受粉する。昨年まで、私は雌花の方を花弁だと認識しないで見ていました(二段目左 雄花 / 右 雌花)
今夏も数珠の実がたくさん成りました。それが・・・昨日の台風でかなり被害を受けてしまい、葉っぱはボロボロに。下手をするとこのまま枯れてしまうかな?数珠の実は約半分ほどがすでに黒く色づいて堅くなっております。今日それらを収穫しました。来年の春まで暗所で保管し、春先にまた植えましょう。
ちなみに数珠玉は多年草ですから、今年の株は根を残しておけばまた来年育つ可能性があります。そうするとうちの庭の数割が数珠玉だらけになってしまうかも知れませんね・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年10月8日 キンモクセイが満開になりました
今年もアパートの入り口に生えているキンモクセイの木が花を付けました。
昨日から今日にかけてが満開かと思われます。
その甘美な香りが辺り一面に漂い、なんとも良い感じ。
キンモクセイは香りが強いので、ほんのり軽く感じる程度が良いですね。
木の下で、目一杯強い刺激を受けると、まるで香水の瓶を直接嗅いだかの
様な香撃を受けてくらくらします・・・
ただ・・・今年はひとつ気になる現象があります。
花が咲く少し前より、キンモクセイの葉がパラパラと落ち始め、
木の下には散り始めたオレンジ色の花弁と同時に落葉が目立ちます。
例年では見られなかったことなので、ちょっとヘンですね・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年10月24日 今年のオナモミの実
数年前より毎年鉢植えで育てているオナモミの実が今年も成りました。
今年の生育状況は、正直言ってあまり芳しくありませんでした。
それは葉っぱがあまり伸びなかったこと。ひょろひょろで途中で
枯れてしまうのでは無いか?と心配する様な雰囲気でした。
一応実が成ったので、何とかまた来年に繋げる事が出来そうです。
色々な植物や生き物の世話をしていていつも気になるのは、次の
世代に橋渡しが出来るかどうかに他なりません。
毎年その繰り返しが出来ることが私のささやかな充実感に繋がる事であります。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2011年10月26日 ホトトギス
庭のホトトギスが次々に開花し始めました。
ごらんの様に派手な形と色をしている花で可憐とは言い難い雰囲気です。
花弁のサイズは小振りです。
一本の茎に複数のつぼみがつきますので群生した花の塊になります。
遠くから見ても目立っているのですぐに気づきますね。
アップで見るとおしべ・めしべは少々グロテスクかも知れません。
西洋花の毒々しさすら感じます。
今の時期には、小さなアブの様な虫たちが花の周りを飛び回って
一生懸命受粉の手助けをしています。
この花が萎れるころ、また一歩秋が深まった事を静かに感じます・・・
FUJIFILM Finepix S5Pro + SIGMA Macro 105mmF2.8→11
F2(フジクロームモード)ISO400 絞り優先モード
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2012年03月22日 今年の梅の花
今年の梅の開花が全国的に約1ヶ月遅れているのはご存じの通り。
例年ならば何処かの梅祭りにでも出かけていた所ですけれど
そのシーズン中にはつぼみのままで、イベントは不発に終わりました。
先日 地元の神社に取材に行った所、梅の花はピークを過ぎて
撮影のタイミングとしたはちょっと遅かった・・・
花弁のアップで見ると、勢いが無くなっているのが一目瞭然です。
仕方がないのでやや引き気味のアバウトな構図でおさえるに留めました。
梅の花が散る来週頃には早咲きの桜が見られるかも?
梅と桜が同時に撮れたらそれはちょっとした面白い景色なんですけど
異常気象の観点からすると心配な状況証拠にもなりそうですね・・・
蛇足ながら・・・ここの所、植物の観察コメントに毎回「今年の・・・」と
わざわざ付けているのは、最近動植物の生態に変化があるかないかに
重大な関心を持っているから出て来る言葉です。
いわずと知れた福島原発事故によって拡散した放射性物質の
環境生態系への影響を懸念しての視点であります・・・
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2012年6月8日 青梅が豊作
関東もいよいよ梅雨に入りそうです。
アパートの庭には1本の梅の木が植わっています。
毎年しっかり収穫しています。
今年は青梅が豊作でした。
その数 約200個!今までで一番では無いかな。
10個ほどはコンクリートの上などに落として割ってしまいましたが、
それでも191個が残りました。
これは実家に送っていつも梅酒にしてもらっています。
ちなみに庭の土壌は現在セシウム濃度が0.1μSv/h前後で
完全に安全であるとは言い難い。
でも大人用に限定して・・・
自己責任の元どう判断するかが求められているご時世なのであります。
最近話題にしておりませんが、
うちでは食物に関してはかなり神経質にセレクトして日頃食材を選んでいるつもりです。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2012年6月12日 白いホタルブクロ
今の時期に山間の小道などを歩いていると ホタルブクロの花はそこかしこに見かける事ができるポピュラーな存在。でもその色は紫が普通でしょう。最近園芸種?として出回っている白いホタルブクロは、もう珍しくなくなりましたね。
私は 5年位まえに花屋さんで見つけて、つぼみが付いた苗を一鉢買って来て庭の片隅に植えた事があったのです。でも土が合わなかったのか、その個体は一週間ほどで枯れてしまった。つぼみが開くのを見る事も無しに・・・
それが今 実家のベランダにしっかりと咲いているでは無いですか。しかも何鉢もあってみな元気。けっこう簡単な世話で咲いたらしい・・・自分が苦労して駄目だったものをこうもやすやすとクリアされると少し悔しいです。私は山野草のやや地味で可憐な花弁が好きかな。西洋花のデカくて派手なのは素敵だとは思えない。まぁその辺りは好みの問題でしょう・・・
最近植物をじっくり観察する気持ちの余裕がちょっと足り無くなってますね。そういう所も自分の意識をはかるバロメーターの一つかと思います。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |
2012年8月11日 ジュズダマの花
今年も庭に植えてあるジュズダマに花が咲きました。
8月から9月にかけて長い期間に次々と咲きますが、今年は若干咲くのが早いかも・・・
元々田んぼの畦に植わっていたジュズダマの実を数個採ってきて植えたら根付いたもの。
これは多年草なので毎年根っこの株からしっかり発芽しますね。
穂にたくさんの小さな花がたくさん付いているのはイネ科の植物の特徴かな。
以前にも紹介した事がありますが、こうして毎年繰り返される事に毎回感動を覚えます。
今年は一体幾つのジュズダマの実が採れるでしょうか。
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |










 「ジュズダマの花」を追記しました。
「ジュズダマの花」を追記しました。 「白いホタルブクロ」を追記しました。
「白いホタルブクロ」を追記しました。 「青梅が豊作」を追記しました。
「青梅が豊作」を追記しました。 「今年の梅の花」を追記しました。
「今年の梅の花」を追記しました。 「ホトトギス」を追記しました。
「ホトトギス」を追記しました。 「今年のオナモミの実」を追記しました。
「今年のオナモミの実」を追記しました。 「キンモクセイが満開になりました」を追記しました。
「キンモクセイが満開になりました」を追記しました。 「数珠玉」を追記しました。
「数珠玉」を追記しました。 「ミズヒキのつぼみ」を追記しました。
「ミズヒキのつぼみ」を追記しました。 「ホテイアオイの花」を追記しました。
「ホテイアオイの花」を追記しました。 「涼を呼ぶ 吊りしのぶ」を追記しました。
「涼を呼ぶ 吊りしのぶ」を追記しました。 「ギボウシの花」を追記しました。
「ギボウシの花」を追記しました。 「今年のネジバナ」を追記しました。
「今年のネジバナ」を追記しました。 「ザクロの花」を追記しました。
「ザクロの花」を追記しました。 「名を知らない赤い花」を追記しました。
「名を知らない赤い花」を追記しました。 「ヒルザキツキミソウ」を追記しました。
「ヒルザキツキミソウ」を追記しました。 「オナモミの実を植える」を追記しました。
「オナモミの実を植える」を追記しました。 「公園の花たち」を追記しました。
「公園の花たち」を追記しました。 「黄花モクレン」を追記しました。
「黄花モクレン」を追記しました。 「桜桃(ゆすらうめ)」を追記しました。
「桜桃(ゆすらうめ)」を追記しました。 「近所のさくら」を追記しました。
「近所のさくら」を追記しました。 「今年もウラシマソウが生えました」を追記しました。
「今年もウラシマソウが生えました」を追記しました。 「白いモクレン」を追記しました。
「白いモクレン」を追記しました。 「シキミの花」を追記しました。
「シキミの花」を追記しました。 「ヒラタケ」を追記しました。
「ヒラタケ」を追記しました。 「畑の落花生は無事収穫されました」を追記しました。
「畑の落花生は無事収穫されました」を追記しました。 「厄除けと根性」を追記しました。
「厄除けと根性」を追記しました。 「彼岸花」を追記しました。
「彼岸花」を追記しました。 「こぶしの実」を追記しました。
「こぶしの実」を追記しました。 「烏柄杓の仏炎苞」を追記しました。
「烏柄杓の仏炎苞」を追記しました。 「烏柄杓(カラスビシャク)」を追記しました。
「烏柄杓(カラスビシャク)」を追記しました。 「擬宝珠(ぎぼうし)」を追記しました。
「擬宝珠(ぎぼうし)」を追記しました。 「白いネジバナ」を追記しました。
「白いネジバナ」を追記しました。 「ホオズキは地下茎で増える」を追記しました。
「ホオズキは地下茎で増える」を追記しました。 「サンシャイン牧場よりリアルな種を」を追記しました。
「サンシャイン牧場よりリアルな種を」を追記しました。 「オダマキの花」を追記しました。
「オダマキの花」を追記しました。 「コウヤノマンネンゴケ」を追記しました。
「コウヤノマンネンゴケ」を追記しました。 「極彩色の花桃」を追記しました。
「極彩色の花桃」を追記しました。 「コケの管理の難しさ」を追記しました。
「コケの管理の難しさ」を追記しました。 「ウラシマソウの復活」を追記しました。
「ウラシマソウの復活」を追記しました。 「すずらんの開花」を追記しました。
「すずらんの開花」を追記しました。 「すずらんの鉢」を追記しました。
「すずらんの鉢」を追記しました。 「エンゼルトランペット」を追記しました。
「エンゼルトランペット」を追記しました。 「オナモミの実のマクロ撮影」を追記しました。
「オナモミの実のマクロ撮影」を追記しました。 「立派なオナモミの実がなりました・・・」を追記しました。
「立派なオナモミの実がなりました・・・」を追記しました。 「オナモミの実が採れそう・・・」を追記しました。
「オナモミの実が採れそう・・・」を追記しました。 「彼岸花」を追記しました。
「彼岸花」を追記しました。 「今秋の収穫 <零余子>」を追記しました。
「今秋の収穫 <零余子>」を追記しました。 「コーヒーの花」を追記しました。
「コーヒーの花」を追記しました。 「これは何の植物だろう?」を追記しました。
「これは何の植物だろう?」を追記しました。 「梅雨は梅を収穫するタイミング」を追記しました。
「梅雨は梅を収穫するタイミング」を追記しました。 「うちのは短形でした」を追記しました。
「うちのは短形でした」を追記しました。 「○○○」を追記しました。
「○○○」を追記しました。